皆さんこんにちは。茨城県内の外構工事・土木工事を承っている株式会社河原井です。弊社は戸建て住宅の外構工事や土木工事、公共工事など幅広い施工が可能で、理想の住まいと安全な環境をご提供いたします。
護岸工事とは、人々の暮らしの安全を守るために欠かせない工事のひとつですが、どんな工事なのか、詳しいことはよく知らないという方も多いでしょう。本記事では、護岸工事の概要や必要性、護岸工法のポイントについて解説します。
■護岸工事の重要性とは?暮らしを守る重要な土木工事

護岸工事とは、河川や海岸の岸辺を補強・保護し、水の流れや浸食から土地や構造物を守るための土木工事です。護岸工事は自然災害から人々の生活や財産を守るために欠かせない工事で、地域の安全と安心を支える重要な役割を担っています。
日本は降水量が多いため、河川の氾濫や土砂災害が発生しやすい国土です。地球温暖化の影響による集中豪雨や大型化した台風などから人々の安全を守るためにも、護岸工事の必要性は年々高まっています。
また、護岸は多用な生物の生息環境である水際部に設置するため、自然環境に対して十分に配慮することが求められます。さらに、施工性や経済性なども考慮したうえで設計や施工を進めることが重要です。
参照:国土交通省「護岸設計の基本」より
◆近年の災害データから見る護岸工事の緊急性
国土交通省の統計によると、日本全国で発生する水害の件数は増加傾向にあります。2018年から2022年までの5年間においては、全国の水害発生件数の年間平均が1,500件を超えており、被害総額は年間約3,000億円に達しています。
茨城県においても同様の傾向が顕著に現れており、気象庁のデータによると、茨城県では以下のような水害や水害リスクが確認されているとのことです。
【豪雨災害の増加】
2019年に発生した台風19号(東日本台風)では、茨城県内において24時間降水量が300mmを超える地点が複数発生し、久慈川や那珂川で氾濫が発生しました。県内で約4,000戸が浸水被害を受け、経済損失は数百億円規模に達しています。
【河川氾濫の頻発】
茨城県内の主要河川では、過去10年間で15回以上の氾濫注意水位超過が記録されています。そのうちの5回は避難勧告の発令に至っており、とくに県北部の久慈川水系と県央部の那珂川水系で多く発生しています。
【海岸侵食の進行】
茨城県の太平洋沿岸では、年間平均1〜2mの海岸線後退が確認されています。海岸侵食の進行による沿岸部の住宅地や農地への影響は、年々深刻化しています。
このままでは、今後は従来の護岸工事基準では対応できない規模の災害が発生することが予想されるため、より高度で確実な護岸工事が必要になるといえるでしょう。
参照:e-Stat「水害統計調査」より
株式会社河原井は、護岸工事についても豊富な実績があります。ぜひお気軽にご相談ください。
■護岸工法の基本的な考え方と技術的ポイント

ここでは護岸工法の目的や重要性、一般的な工法や特種な工法、技術的な留意点について解説します。
1. 護岸工法の目的と重要性
護岸工事の目的は、河川や海岸の岸辺を補強・保護し、水の流れや浸食から土地や構造物を守ることです。そして護岸工法とは、河川や海岸の水による土地の侵食や崩壊を防ぐための工法です。
道路などのインフラや農地、街などを災害から守るためには、護岸工事によって岸辺をしっかりと補強・保護することが求められます。とくに近年は集中豪雨や大型化した台風によって皮の水位が急増するなど、災害リスクも高まっているため、護岸工事の必要性も高まっているといえます。
2. 一般的な護岸工法
護岸工事にはさまざまな工法があり、施工箇所の状態やコストなど、さまざまな要素を考慮して適切な工法を選ぶことが求められます。ここでは一般的な工法である「重力式護岸」「もたれ式護岸」「練積み護岸(ねりづみ)」の3つについて解説します。
まず、「重力式護岸」とは、大きくて重いコンクリートブロックや石を積み重ねることで、ブロックや石自体の重さで岸を安定させる工法です。構造がシンプルで工事がしやすく、比較的コストも抑えられるのがメリットです。
「もたれ式護岸」は、背後の土の重みを活かして支える構造の工法のことをいいます。施工箇所の地形に合わせやすく、少ない材料で施工可能な点がメリットです。
「練積み護岸(ねりづみ)」は、石をモルタルなどで固めて積み上げる工法です。仕上がりの見た目が美しく、丈夫で長持ちするため、住宅地や公園付近にも適しています。
3. 特殊な護岸工法
地盤の弱い場所や環境保護を重視する現場など、一般的な工法では対応が難しい場所では次のような特殊な工法で施工します。
「深層混合処理工法(しんそうこんごうしょり)」という工法は、地中にセメント系の固化材を混ぜ込んで強固な地盤をつくる工法です。地中のやわらかい地盤を改良するため、大雨などで地盤が崩れやすい場所に有効です。
「テールアルメ工法」は、「補強土壁」とも呼ばれ、鉄筋などの補強材を入れた盛土で垂直に近い護岸を作る工法のことを指します。限られたスペースに高い護岸を作る際に適している工法です。
「緑化護岸工法」は、植物を使って護岸を覆い、自然に近い景観を保ちながら岸を守る工法です。生き物の生育環境を守ることにもつながり、環境に配慮した工法として注目されています。
4. 技術的な留意点(設計から維持管理まで)
護岸工事では、工程ごとに注意すべきポイントがあります。まず、設計時には、川の流れの速さや周囲の土の性質、環境への影響などを丁寧に調査し、施工箇所に合った工法を選ぶようにしましょう。工事中は、図面通りに施工が進んでいるか、材料に問題がないか、安全に作業が進められているかを確認しながら進めます。
護岸の完成後は、長く安全に使い続けるために定期的な点検や補修が必要です。とくに豪雨や地震が発生した際には、すぐに被害の有無を確認し、必要に応じて補修することが重要です。
参照:国土交通省「4.護岸エ法」より
株式会社河原井は、護岸工事についても豊富な実績があります。ぜひお気軽にご相談ください。
■茨城県の株式会社河原井の確かな技術と信頼の実績
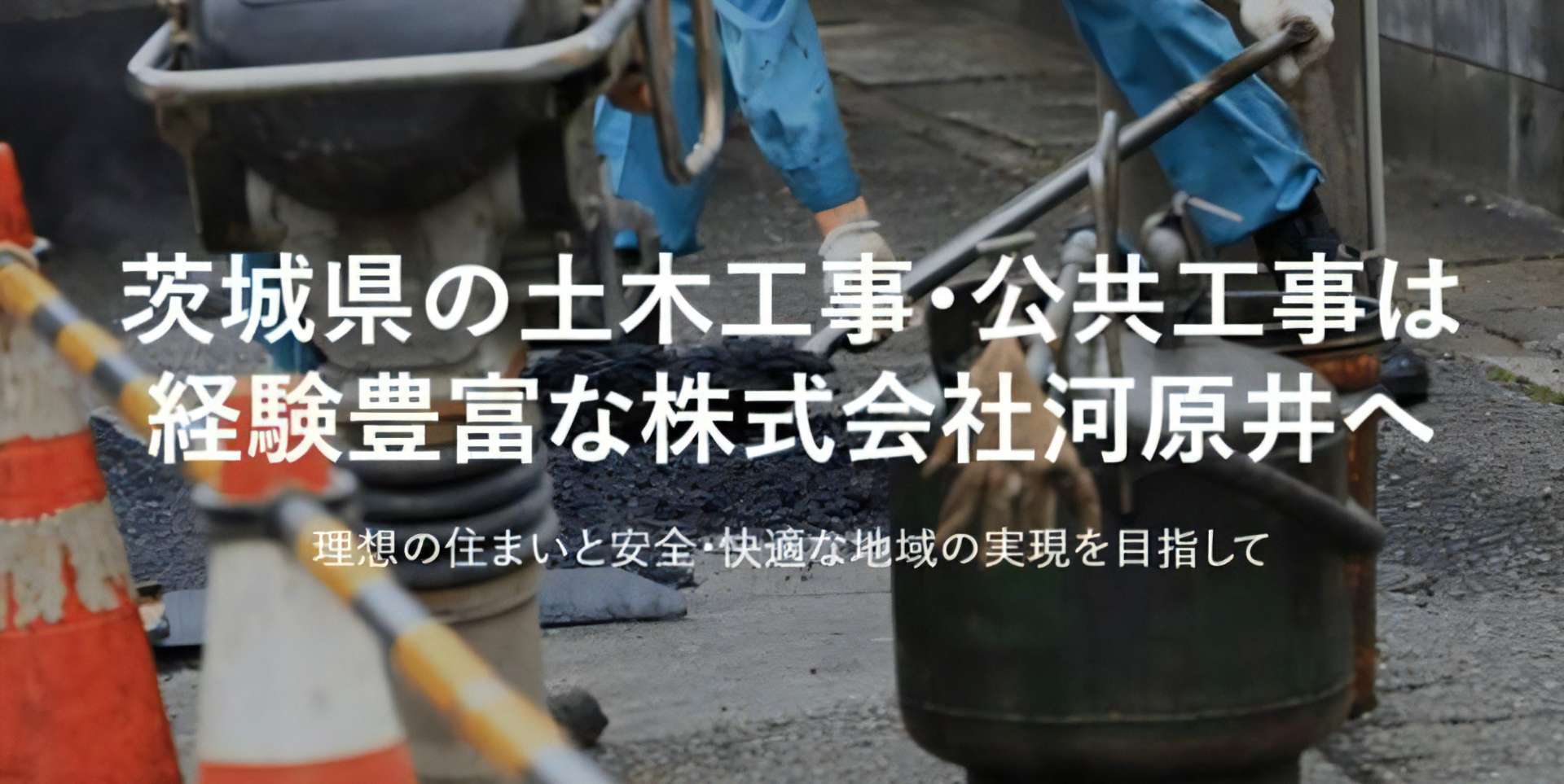
茨城県を拠点に活動する株式会社河原井は、護岸工事をはじめとした公共・民間の土木工事を多数手がける地域密着型の施工業者です。安心・安全な護岸工事は、ぜひ茨城県の株式会社河原井にお任せください。
◆河原井の強み
土木のプロ集団として、外構工事から河川・道路・造成まで幅広く対応可能です。全工事に責任施工で対応しております。地元行政からの受注実績も多数あり、公共事業で培った信頼
や、安全・品質・環境に配慮した施工が好評です。
また、弊社は施工前の現地調査からアフターケアまで一貫対応しており、確かな施工管理体制で、近隣対策や安全管理も徹底しております。
弊社は災害対策工事にも強く、河川の氾濫や海岸侵食、地盤沈下など、複雑な条件下でも確実な対応力で施工いたします。
護岸工事をご検討中の方は、ぜひ株式会社河原井へご相談ください。地域の安全を守るお手伝いを、私たちが責任をもって担います。
アフターフォローも充実しており、施工後のお悩みやご不満、施工箇所以外のトラブルにも対応しておりますので、遠慮なくご連絡ください。


